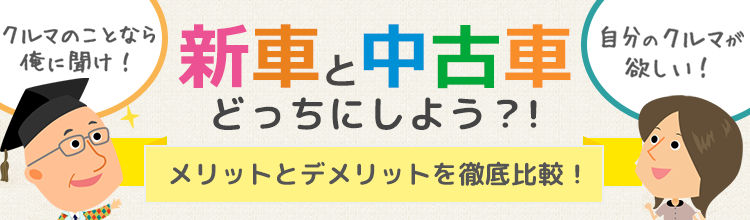EV(電気自動車)
2025年度(令和7年度)CEV補助金の対象車や補助額について解説。令和6年度との違いや補助額に変更のあった車種などもご紹介します。また、令和6年度中に対象車を購入して申し込みが間に合わなかった方への対処法も解説していますので、参考にしてください。
EVを購入する理由には、ランニングコストの安さや補助金といった税制優遇があるといったガソリン車よりお得感があることがあげられるだろう。一方でEV購入にあたって車両価格の高さや航続距離が短いことに懸念を持つ人もいるだろう。 EVが我が国の市場に出て…
第一回の対談ではEVが認知される前の取り組みについて紹介しました。 今回は量産型EVの登場から現在にかけて、EV普及の経緯や我々がEVとどう付き合っていけばよいのかを考えてみました。
2022年はEV元年ともいわれ、EV普及をより身近に感じるようになったかもしれない。EVの歴史は古く、1970年代から様々な取り組みがなされていた。ガソリン車からEVに置き代わる時代の変化を知るために、一般社団法人日本EVクラブ代表の舘内 端氏との対談を紹介…
日本では普及率の低い電気自動車(EV)。世界各国ではEVの普及が進む一方で、課題も見えてきています。ここでは日本でEVが普及しない理由、将来の普及率に関する予測、EV普及後の課題、今後EVを買うべきかどうかを解説しています。
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の購入時と、V2Hなど充電インフラ導入時に交付を受けられるCEV補助金。2023年3月23日より、車両購入に対する令和4年度補正予算分の申請受付が開始されました。交付条件や補助金の支給額、2022年度との違…
電気自動車やPHEVの普及に伴い、V2Hを導入する人も増えています。ここではV2H充放電設備と家庭用蓄電池や普通充電器との違い、導入コストや補助金、対応車種などの情報をまとめています。設置場所などよくある質問にもお答えしていますので、参考にしてくだ…
短いと思われがちな電気自動車の航続距離。しかし最近は500㎞以上走行できるような電気自動車も増えています。ここでは電気自動車の航続距離の目安とともに、国産・外車の代表車種の航続距離をランキング化してご紹介しています。また充電時間などの質問にも…
V2HとV2Lは、車から建物や家電機器などに給電するシステムのことです。ここではそれぞれの特徴やメリット・デメリット、導入をおすすめする人、本体価格など導入にかかる費用、補助金は出るのかなどを解説しています。
電気自動車(EV)は高いといわれます。ここでは国産EVの車両価格一覧、EVが高い理由の解説とともにガソリン車との価格差、走行時の電気代・ガソリン代を比較しています。将来的に価格が安くなるのかも解説していますので、参考にしてください。
車から自宅などの建物に電力を供給できるV2H。全ての電気自動車(EV)やPHEVがV2Hに対応している訳ではなく、特に輸入車の場合は対応車種が少ないので注意しましょう。ここでは最新のV2H対応車種を紹介するとともに、よくある質問にも回答しています。