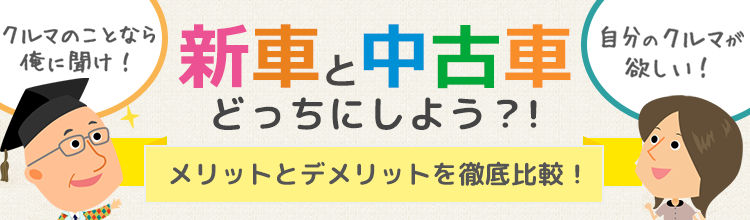- この記事の目次 CONTENTS
- スカイアクティブテクノロジーとは?
- マツダが内燃機関にこだわり続ける理由
- 世界初のSPCCI技術とは?
- アクセルレスポンスの良さ!
- 実用的なエンジンフィーリング!
- キレのあるハンドリング・スポーティな走り
- スカイアクティブXのデビューは2019年?
スカイアクティブテクノロジーとは?
マツダのスカイアクティブ(SKYACTIV)テクノロジーとは、抽象的な表現だ。マツダは、すべての人に「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」をお届けするため世界一の機能を最も効率的につくる。それが、「スカイアクティブ テクノロジー(SKYACTIV TECHNOLOGY)」の出発点と説明する。
端的に言えば、スカイアクティブとは新技術の呼び名だ。このスカイアクティブテクノロジーには、エンジンやプラットフォーム(車台)、ミッションなど多くのものが含まれる。カッコいい響きを持つが、まぁ、とにかく分かりにくい。
今回そのスカイアクティブ テクノロジーが更に進化。この進化したスカイアクティブは、次期新型アクセラに搭載される予定。その新型アクセラのプロトタイプに試乗した。

マツダが内燃機関にこだわり続ける理由
次期新型アクセラには、ザックリふたつの新スカイアクティブ テクノロジーが採用されている。ひとつは、究極のエンジンといわれるHCCI技術を応用した世界初の「火花点火制御圧縮着火(Spark Controlled Compression Ignition:SPCCI)」を採用した「スカイアクティブ・エックス(SKYACTIV-X)」。そして、次世代車両構造技術「スカイアクティブ・ビークル・アーキテクチャー(SKYACTIV-Vehicle Architecture)」だ。
今回注目したいのは、スカイアクティブX。SPCCI技術により、燃費は20~30%程度アップするという。現行のアクセラ2.0Lガソリンエンジンの燃費は、19.0㎞/Lだったので、燃費が20~30%アップすると22.8~24.7㎞/Lという燃費値になる。確かに低燃費であるものの、ハイブリッド車並というレベルには達していない。
すでに、欧州ではEV(電気自動車化)を加速させるというアピールが続いている。今後、化石燃料を使うエンジンは、衰退していく一方になるだろう。それなのに、なぜ、あえてマツダは未だに内燃機関にこだわるのだろうか?
トヨタとの提携もその背景に

ただ、マツダも長期に渡り内燃機関にこだわるつもりはないようだ。スカイアクティブXを開発を続けながら、EVなどの電動化車両の開発も並行して続けているとしている。
しかし、少なくとも完全EV化になるまでの数十年間の間、内燃機関は存在しCO2を排出していく。現在のEVも火力発電で電力を供給しているのであれば、「Well-to-Wheel(燃料の採掘、生産から車両走行に至るまで)」のCO2排出量は大差ないともいう。つまり、マツダはEV化を含んだ電動化を開発しながら、完全EV化になるまでの間、内燃機関もまだまだやれることがあるというのがマツダの考えでもある。
もちろん、キレイごとだけでない。マツダはトヨタと提携した。トヨタを中心として、オールジャパンで電動化技術の開発が進められている。つまり、マツダ単独で電動化技術を開発しなくてもよいというのも、マツダが目の前にある内燃機関にこだわり続けられる理由でもある。
世界初のSPCCI技術とは?
さて、試乗したのは世界初の「火花点火制御圧縮着火(Spark Controlled Compression Ignition:SPCCI)」を搭載したスカイアクティブXと、新プラットフォームを採用した次期新型アクセラのプロトタイプだ。
注目のスカイアクティブXは、2.0L直4エンジンにルーツ式スーパーチャージャーが組み合わされている。スカイアクティブXは、HCCI(予混合圧縮着火)を応用している。HCCIは高圧縮で混合気が自己着火することで、高い燃焼効率となり、同時にリーンバーン化し低燃費化が可能となる。
ただし、安定して自己着火させるためには、一定の条件下でないと難しく、自動車のエンジンのように常にエンジンの使用環境が異なる条件下では自己着火が安定せずノッキングを起こす。これでは、クルマのエンジンとしては使えない。マツダは、その自己着火をスパークプラグで制御した技術がSPCCIとなる。

アクセルレスポンスの良さ!
アクセラのプロトタイプに試乗すると、すぐに感じるのがアクセルレスポンスの良さだ。
これは、スカイアクティブXの空燃比にある。スカイアクティブXでは、空燃比は30~40の間を多く使うという。理論空燃比は、14.7なので2倍以上。当然、燃料が少なくなるので低燃費化できる。これだけの量の空気を吸い込むために、スーパーチャージャーが必要だったりする。より多くの空気を吸い込むために、スロットルバルブは大きく開いたまま。そのため、ポンピングロスが少なくレスポンスのよい加速が楽しめる。

燃費のよい領域でエンジンを回すと、まるでディーゼルエンジンのようなガラガラとしたサウンドが車内入る。プロトタイプなので、遮音が完璧ではないことも理由なのだが、あまり心地のいいサウンドではなかった。
実用的なエンジンフィーリング!
スカイアクティブXの目標出力は、190ps&230Nm。Cセグメントのアクセラであれば、十分なスペック。レスポンスの良さと230Nmという最大トルクの恩恵で、非常に力強い加速を楽しめる。
ただし、まだ開発途中ということもあり、エンジンフィールはやや微妙。高回転域までスパーンと伸びてパンチのあるパワーを感じるというようなエンジンではない。
ダウンサイジングターボのように、高回転でエンジンの伸びは鈍くなりパンチも無くなる。実用的なエンジンといった印象で、スポーティさは感じられなかった。
また、ミッションも6ATのまま。今や10速ATなどもある時代に突入している。7速や8速といった多段化がされれば、燃費面でも、よりエンジンの燃焼効率のよい回転数が使えるので効率も上がる。高速道路などでも、エンジンの回転数を下げることもでき静粛性も増すなどメリットは多い。そろそろマツダは、6速ATから脱却したいところだ。

キレのあるハンドリング・スポーティな走り
そして、アクセラプロトタイプには新プラットフォームが採用された。これにより、リヤサスペンションが従来のマルチリンクからトーションビームに変更されている。一般的には、リヤサスはグレードダウンされている。
マツダは、これをコストダウンのためではないと言う。トーションビームでも、目標とする乗り心地や操縦安定性を確保できたからだという。その目標値がどれほどのものか分からない。しかし、マルチリンクならもっと良くなるのでは? と、思うのは当然のことだ。
実際に乗ってみても、リヤサスの形式だけではないものの、タイヤのゴツゴツ感はしっかり出ていて、しっとりとした乗り心地や安定感は感じられなかった。今後の進化に期待したい部分だ。
ただ、回頭性など俊敏性はなかなかのもので、キレのあるハンドリングを披露。気持ちの良い走りが期待できる。
また、シートを好印象。腰がしっかりと支えてくれるので、カーブで横Gがかかっても姿勢変化が少ない。

スカイアクティブXのデビューは2019年?
今回のアクセラプロトタイプが、新型アクセラとなって登場するのには、まだしばらく時間がかかる。現行アクセラは、2013年にデビュー。6年でフルモデルチェンジとする2019年が、次期新型アクセラのデビューイヤーと予想できる。
次期新型アクセラの登場まで、まだ1年以上ある。スカイアクティブXもより進化するだろう。EV化の波に一石を投じるスカイアクティブX。マツダファンでなくても注目のテクノロジー。早期の登場に期待したい。
アクセラのカタログ情報

- 平成25年11月(2013年11月)〜令和1年5月(2019年5月)
- 新車時価格
- 171.2万円〜331.0万円
アクセラの在庫が現在5件あります
以下車両の保証内容詳細は画像をクリックした遷移先をご確認ください。