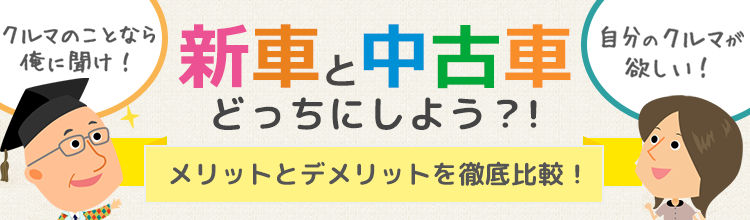ホイールナットはどんなものでも使えるわけではありません。車両とホイールに合ったサイズ・種類のものを使わなければハブボルトやホイールナットが損傷するだけでなく、最悪の場合ホイールナットが緩んでタイヤが脱落する危険もあります。
正しく理解していただくために、メーカーごとに標準で使われているホイールナットの種類について解説し、社外品を使う場合の選び方のポイントなどを紹介します。
ホイールナットの種類
ホイールナットは種類ごとに主に以下のような違いがあります。
- ナットの座面形状の違い
- ネジピッチの違い
- 貫通ナットと袋ナット
- ナット径の違い
適合するものとは異なる形状のホイールナットを取り付けることは絶対NGで非常に危険です。
装着しているホイール、車のハブボルトに合ったホイールナットを慎重に選択しなければいけません。
また、ここでは各種類ごとに適合するメーカーも解説していますがOEM車両は除きます。
座面形状の種類

座面とはホイールナットとホイールが接する部分のことを指します。
座面形状には大きく分けて3つの形状があります。
- テーパー座
→テーパーナットを使用。すべてのメーカーで採用実績あり。社外ホイールもほとんどがテーパー座を採用。メーカーを問わず、スチールホイールもテーパーナットを使う。 - 球面座
→球面ナットを使用。ホンダ車のアルミホイールで採用 - 平面座(平座)
→平面座ナット(ストレートナット)を使用。トヨタ車、レクサス車のアルミホイールで採用。一部の三菱車、日産車のアルミホイールでも採用している車種がある
テーパーナットの座面部は、ホイール側もナット側も60°になっています。
製造コストをもっとも抑えることができるナットで、社外品ホイールも多くがテーパーナット対応となっていることから、汎用性の高いホイールナットとも言えます。
球面座はよく見ると、座面が球面という名前のとおり丸みを帯びた形状をしていますが、一見テーパーナットと見た目が似ており混同しないように注意が必要です。
テーパー座や球面座がナットを締め込むことでセンターが出る構造なのに対して、平面座ナットは面でセンターが出る構造となっており、安定した締結構造となっています。
ホイールナットの中ではもっとも作りが複雑なため製造コストが高く、主にトヨタ車やレクサス車で使われているナットです。
ねじピッチの違い

ねじピッチとは、ねじ山とねじ山の間隔の広さのことを指します。
P1.25よりP1.5の方がねじ山の間隔が広いボルトでそれぞれに互換性はありません。
そのため、誤ったねじピッチのナットを使うとハブボルトとホイールナットのねじ山を損傷させるに留まらず、最悪の場合にはハブボルトの折損、それによって走行中に車両からタイヤが脱落してしまう恐れがあります。
慎重かつ注意して、車に合ったホイールナットを選定する必要があります。
それぞれの自動車メーカーで採用されているねじピッチは以下のとおりです。
- P 1.25…スズキ、スバル、ニッサン
- P 1.5…ダイハツ、トヨタ、ホンダ、マツダ、ミツビシ、レクサス
貫通ナットと袋ナット

貫通ナットはほとんどの場合でスチールホイールに使用されるナットです。
ナットの両端が貫通している形状なので、ナットを締めていくとナットの穴からハブボルトが出てくる構造です。
一方で袋ナットは穴が貫通しておらず、ハブボルトが見えない構造になっています。
見映えが良く、ハブボルトの錆を防止するメリットがあり、多くはアルミホイールで採用されているホイールナットです。
注意点として奥行きの浅い袋ナットとロングタイプのハブボルトを組み合わせると、ナットの座面がホイールの座面に当たる前に、それ以上締まらなくなる…という可能性があります。
ホイールナットのサイズ
ホイールナットは座面形状やねじピッチの違い、貫通/袋ナットの違い以外にもサイズそのものの違いにより、ホイールへの取り付け可否が決まることがあります。
ナット径の違い
ナット径は工具を掛けるホイールナットの頭の部分のサイズのことを指します。
ナット径が異なれば、使用するソケットのサイズも異なります。
- 21mm(21 HEX)…トヨタ、ダイハツ、日産、マツダ、三菱、レクサス
- 19mm(19 HEX)…スズキ、スバル、ホンダ
- 17mm(17 HEX)…一部年式のマツダ
純正のホイールナットはおおむね、21mmと19mmに二分されます。
ナット径が小さければ、ホイールナットそのもののサイズをコンパクトにすることが可能です。
※HEXはヘキサゴン(六角形)の略。
社外品のアルミホイールに交換するときの注意点
社外品のアルミホイールを装着するときは、ホイールナット本体のサイズについても確認が必要です。
社外品のアルミホイールはデザインの観点から、ナットホールが狭くなっているものが多いです。
よって、ホイールナットをハブボルトに掛けることができても、それを締め付けるための工具(ソケット)が入らない、もしくはクリアランスがギリギリになるため、ホイールに傷を付けるリスクが高くなることが考えられます。
わたしも自分の車でその経験があり、社外品ホイールの保護のため純正では21 mmのナットを、対応品の17mmのナットに交換したことがあります。
ロングタイプのナットに注意
スチールホイールに長い(深い)ホイールナットを使用すると、締め付けそのものは問題なくてもホイールキャップが干渉することがあるので注意しましょう。
干渉することでホイールキャップに変形が発生したり、取り付けができなくなる可能性があります。
また、アルミホイール・スチールホイール問わずロングタイプのナットを使用したことで、ナットが車両の全幅よりハミ出している場合、保安基準不適合で車検に通らないので注意が必要です。
ホイールナットの選び方のポイント
ホイールナットの選び方で最も重要なのは、ここまで説明してきたように繰り返しになりますが、以下の条件に車両・ホイール側がマッチするかどうかです。
- ナットの座面形状の違い
- ネジピッチの違い
- 貫通ナットと袋ナット
しかし、これらの物理的に合う合わないの違いだけではなく、デザイン性や素材の違いもあるので、もし社外品に交換するとなった場合には非常に多くの選択肢があります。
見た目や値段に惑わされないで
ホイールナットはピンからキリまで様々な商品が販売されていますが、「見た目がカッコいい、色が魅力的、その割に値段がお手頃…」といった理由だけでホイールナットを選ばないように注意してください。
中にはコピー品も流通しており、あまりに相場とアンマッチな値段のホイールナットは粗悪品の可能性があります。
そういったナットは精度が悪く、ナットの中心がズレていたりホイールとの接触面が不均一、ねじ山を損傷させるリスクがあったり、最悪の場合は規定トルクで締めたにも関わらず緩みが発生するような事例も発生しています。
こうした商品を手にしないためにも、その判断に自信のない方は、普段からお世話になっている整備工場や車屋さんに相談することをおすすめします。
純正同等の品質であればスチール製でOK
純正アルミホイールに採用されているホイールナットの多くはメッキ処理が施されたスチール(合金鋼)製です。
ホームセンターで販売されていることもあり、安価で手に入りやすいベーシックなタイプです。
特にこだわりなどがなければ、スチール製のもので十分です。
たとえば、こちらの商品はトヨタの純正タイプのホイールナットですが、ブラックやレッドで色味に変化を与えることができます。
社外品のアルミホイール用でもこだわりがなければ、以下のようなスチール製のベーシックな袋ナット(テーパー座)で必要十分です。
防犯性能も兼ね備えたホイールナット
純正のホイールナットの頭は六角形状となっているので、一般的な工具を使用しての脱着が可能です。
誰でも簡単に交換できる一方で防犯面で劣ります。
そこでホイールの盗難リスクが気になる方は、専用のアダプターが無ければ緩めたり締めたりできないホイールナットを使うのがおすすめです。
ロックナットを使うのもありですが、使用するホイールナットすべてを防犯性能を兼ねたものに交換するのもおすすめです。
こちらは「七角形」という特殊な多角形ホイールナットになっており、脱着には専用のアダプターが必要になります。
スタイリッシュな見た目もアクセントになります。
また、素材は「クロームモリブデン鋼」が使われており、純正でも使われるスチール製と比較して錆びにくく、軽量でもあるに関わらず強度に優れていることから、レースシーンでも使われることがあります。
価格が高くなる傾向にありますが、わたしもマイカーにはこの製品の色違いを使用しています。
よくある質問:トヨタなどのホイールナットの適合表は?
トヨタのアルミホイール用のホイールナットは基本的に「M12×P1.5 平面座」を使用します。
トヨタの多くの車種ではこれを基準に選べば間違いはありませんが、中には種類の異なるホイールナットを採用しているものもあるので注意が必要です。
「M12×P1.5 平面座」以外のホイールナットを使用する車種の例
代表的な該当車種は以下のとおりです。(一部の車種例を紹介)
- M12×P1.25 テーパー座
→86で採用。スバルBRZと共同開発車種で、スバルで採用されるホイールナットに準じる - M14×P1.5 平面座
→ランドクルーザー、40系アルファード /ヴェルファイア等で採用。レクサスブランドでは、LS・LX・LM・GX・LCといった大型車種を中心に採用。 - M12×P1.5 テーパー座
→コペンGR・タンク/ルーミー・パッソ・ライズ・ピクシス○○(軽自動車)等で採用。いずれもダイハツからのOEM車両。
また、基本的にトヨタ車のスチールホイールの場合はテーパー座のナットを使用
大まかに言うとトヨタ以外のメーカーが製造しているOEM車両の場合、トヨタ車のアルミホイールであってもテーパー座が採用されています。
スバルが製造している86は座面だけでなく、ねじピッチも異なるので注意が必要です。
また、トヨタ・レクサスの中でも大型車種に採用されるホイールナットはM14というサイズで、通常のホイールナットよりナットの穴が大きいものが採用されています。(ハブボルトもM14でM12と比較して太い)
トヨタ車に限らずですが、装着している・する予定のホイールにどんなホイールナットが合うかは、実際に車を見てもらいながらディーラーに相談するのが確実でしょう。
【補足】トヨタやホンダ車で社外品のアルミホイールに交換するときの注意点
トヨタ、レクサス、ホンダ車のアルミホイール装着車に、社外品のアルミホイールを取り付けるときは、ホイールナットの交換もセットになります。
すでに解説したように社外品のホイールは基本的に座面がテーパー座なので、平面座や球面座のホイールナットは使用不可なためです。
最近では純正ナットに対応した車種専用設計のアルミホイールも出ているようですが、ごく一部に限られるので注意しましょう。
整備士のまとめ
ホイールの違いによる適材適所と、メーカーごとの種類の違いを確実に理解しておかなければ、誤ったホイールナット選びをしてしまう恐れがあります。
物理的に装着ができないだけなら後戻りできますが、座面形状が異なっていたり、粗悪なホイールナットだと装着できても正しく締め付けができずに最悪の場合、ホイールが脱落してしまうリスクを伴います。
よって、ホイールナット選びですこしでも心配や不安を抱えている場合は、普段お世話になっている整備工場やディーラーで車のプロにアドバイスをもらうことをおすすめします。
- Supervised by 整備士 ヒロ
-

保有資格:2級整備士。国産ディーラー整備士、輸入車ディーラー整備士の経験がある、現役の整備士。 整備士経験は10年以上で過去にはエンジニアとして全国規模のサービス技術大会に出場。 車の整備に関する情報をtwitterで発信している。