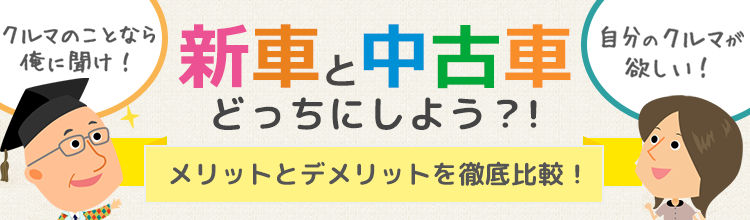- この記事の目次 CONTENTS
- エンジンがかからない原因は?
- 車のエンジンがかからないときの確認項目一覧
- エンジンがかかるかの確認手順
- 症状別のエンジンがかからないときの対処法
- 原因が分からなければロードサービスを利用
- 日頃のメンテナンスが大切
車のエンジンがかからなくなる原因は複数あります。
車に不具合があったり、部品の交換が必要で車屋さんに頼らなければいけないこともありますが、実はドライバー自身で簡単に対応・確認できることもあります。
この記事ではエンジンがかからない原因や、その時の対処法について現役整備士が解説します。
車のエンジンがかからない原因は?
エンジンがかからない原因として大きく分けると以下の3つのパターンがあります。
- ガス欠
- 操作ミス・ユーザー自身で簡単に対応できるもの
- 車の不具合・故障
ガソリンが十分に入っていることをまずは確認し、そのうえでよくある5つのエンジンがかからない原因を解説します。
シフトがパーキングに入っていない
シフトはパーキング(Pレンジ)に入っていますか?
エンジンは安全のために、シフトポジションがP(パーキング)もしくはN(ニュートラル)レンジに入っている時しか、エンジンをかけることはできません。
これは、R(リバース)やD(ドライブ)レンジなどの走行レンジに入っている場合にエンジンがかかってしまうと、意図せずに急に車が走り出してしまいかねないからです。
シフトがP(またはN)レンジにあるかを、レバーやボタン部を目視で確認し、さらにメーター内の表示も「P」(またはN)になっているか確認しましょう。
ハンドルロックがかかっている
ハンドルロックはハンドルが固まり回らなくなる、防犯機能のひとつです。
エンジンをかける時は、この機能を解除する必要があります。
ハンドルロックの解除方法について、くわしくはこちらの関連記事をご参考にしてください。
電子キーの電池が切れている
現在販売されている車の多くは、エンジンをかけるときはキーを挿して回すのではなく、プッシュボタンを押してかけるタイプです。
電子キーが車内にあることを、キーと車側が電波による通信で認証をおこない、エンジンをかける許可を出します。
電子キーの電池が切れていると、この通信が行えずに車側がエンジンをかける許可を出せません。
電子キーの電池切れ時の対処法について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
バッテリーが上がっている
バッテリーが上がっていると、エンジンがかかりません。
これは、エンジンをかけるためのセルモーター(スターター)がバッテリーの電力が弱くて回すことができないからです。
バッテリー上がりの詳しい原因やバッテリー上がりに似た症状の対応について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
部品が故障している
車の部品が故障していてエンジンがかからない可能性もあります。
症状によって故障の原因は多岐にわたります。
この場合はユーザー自身で診断・修理することは困難です。
車のエンジンがかからない場合の確認項目一覧
エンジンがかからない時に簡易的に確認する方法をまとめました。
- エンジンキーが回るか確認(プッシュスタートボタン式除く)
- バッテリー上がりかを確認する
- ガガガ・カチカチと異音がする
- キーを回す、またはプッシュスタートボタンを押しても無音
- セルモーター(スターター)が回らない
- ライト・電気類が点灯しない
- ブレーキペダルが重い
- 冬場でエンジンがかからない
これらの症状について深掘りします。
エンジンがかかるかの確認手順
エンジンがかかるかどうかを、ユーザー自身で簡単に確認する手順を解説します。
エンジンキーが回るか試す
キーシリンダにキーを挿して回す車の場合は、キーが回るか試します。
これは、ハンドルロックしているかどうかの確認です。
キーが回らなければ、ハンドルロックにより動き代は少ないですが、ハンドルを左右に小刻みに振りながらキーを回します。
もしこれでキーが回れば、ハンドルロックが解除されてキーを回せるようになったということです。
(プッシュスタートボタン式の場合、ハンドルロックは自動で解除されるもの、同じようにハンドルを振りながらボタンを押すタイプがあります。)
バッテリー上がりを確認する
ハンドルロックが解除され、普段どおりにエンジンをかけることができるようになれば次の手順です。
バッテリーが上がっていないを確認します。
まずはIG-ONの状態(キーを回すが、ひねらずエンジンをかけない状態。プッシュスタートボタン式の国産車であれば、OFFの状態からブレーキを踏まずにボタンを2回押した状態)で、以下を確認します。
- メーター内の照明やルームランプなどはいつものように明るいか
- ナビ、エアコン、ETC、ドラレコ などの電装用品は普段と同じように起動するか
- 上記の装備が何もしていないのに再起動したり、チラついたりしないか
上記に当てはまる場合は、バッテリー上がりの可能性が高いです。
バッテリー上がりの対処法については以下の記事をご参考にしてください。
【症状別】エンジンがかからない場合の対処法
エンジンがかからない原因として以下の4つのパターンについて解説しました。
- シフトの位置がP(N)になっていない
- ハンドルロックがかかっている
- スマートキーの電池切れ
- バッテリーの寿命
ここまでで解決できておらず、以下の症状に当てはまる場合について、くわしく解説します。
- ガガガ、カチカチと異音がする
- キーを回しても無音
- セルが回らない
- ライト、電気がつかない
- ブレーキが重い
- 冬場でエンジンがかからない
ガガガ、カチカチと異音がする
このような音がするときは、バッテリー上がりの可能性が高いです。
バッテリーが弱くなりセルモーター(スターター)を完全に動かす電力はないが、ある程度は動かそうとできる状態です。
しかし、セルモーター本体の不具合の場合もありますが、切り分けるためにもまずは新品のバッテリーに交換するのがベストです。
キーを回しても無音
無音である場合も、バッテリーが上がっている可能性があります。
この場合は、先ほどの異音がする状態のときよりもさらにバッテリーが弱り、セルモーターを回すことすらできない状態になっていると考えられます。
バッテリーが原因でなければ、考えられる要因は多岐に渡りますが、その場合は車の不具合の可能性が高いです。
セルが回らない
セルモーターが回らないときも、バッテリー上がりである場合と、車の不具合である場合があります。
バッテリー上がりの症状に心当たりがある、またバッテリーを2〜3年以上未交換である場合は、まずバッテリーを交換してみるとよいでしょう。
ライト、電気がつかない
ライト・電気、電装品がつかないのはバッテリー上がりの症状です。
フューズ切れも考えられますが、エンジンがかからないような不具合に至るフューズが切れるには、ほかに重大な理由があります。
ここまでの対処法と同様に心当たりがある場合は、まずバッテリーの交換をしてみましょう。
ブレーキが重い
スマートキーで、プッシュスタートボタン式の車の場合は安全のために、ブレーキを踏んでおかなければ、エンジンがかかりません。
エンジンが切れている状態でブレーキペダルを踏む(特に数回踏めば踏むほど固くなる)と、倍力装置内の負圧が抜けてブレーキペダルが重くなります。
ブレーキが重くなると、ブレーキを踏んでいるつもりでいても重く固いぶん、十分に踏めていないことがあります。
そうなると、ブレーキを踏んでいることを検知するスイッチがONにならず、エンジンをかけることができません。
この場合はいつもより強めにしっかりブレーキを踏み、可能であればブレーキランプが点灯していることを確認しながら、エンジンをかけます。
ブレーキランプが点灯していれば、ブレーキペダルをきちんと踏み込めている証拠です。
冬場でエンジンがかからない
温暖な地域のひとには馴染みのない症状かもしれません。
気温が氷点下になる地域では、車の部品が凍ることでエンジンがかけられないこともあります。
また、ディーゼル車の場合は給油する軽油にも気を付ける必要があります。
これは軽油の性質上、凍ってしまいエンジンをかけることができないことがあるからです。
軽油は地域や季節によって、それに応じた燃料が使われます。
冬(寒冷地)は凍りにくい軽油が使われます。
よって以下のような場合は、軽油の凍結でエンジンがかからない可能性があります。
- 走行距離が少なく、入っている燃料が夏〜秋に給油したもの
- 雪の降らない地域(最高気温が氷点下より上回る地域)で給油した後に、寒冷地に来た車
原因が分からなければロードサービスを利用
解説してきた方法を試しても、エンジンがかからない、または当てはまらない場合はロードサービスを利用することをおすすめします。
JAFに加入している場合は短縮ダイヤル「#8139」で電話がつながります。
最近は多くの任意保険に、ロードサービスが付帯されています。
任意保険のロードサービスを使うときは、保険証券を見れば連絡先や、簡単なサービス内容が記載されています。
手配ができれば、その後はロードサービスによる現地修理または、最寄り・かかりつけの車屋へのレッカー搬送となります。
ロードサービスを個人で手配するのが分からない、難しい場合は一度、直接かかりつけの車屋さんに相談してみましょう。
日頃のメンテナンスが大切
「車のエンジンがかからない」とひとえに言っても、さまざまな原因が考えられます。
原因の大半を占める【バッテリー上がり】【スマートキー の電池切れ】などは、日頃のメンテナンス不足が要因のひとつです。
愛車の健康を維持し、未然にトラブルを防ぐためには、ご自身による日頃のメンテナンスはもちろんのこと、定期的にプロの手によってメンテナンスすることがとても大切です。