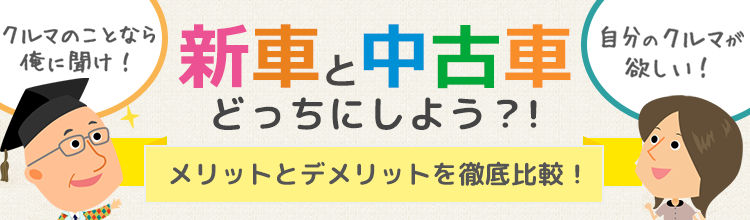金持ち向けから大衆向けへの変化
北京モーターショーで目立ったのはコンパクトカーの出品だ。新興の自動車市場は最初、大金持ちのユーザーからクルマに乗り始めるため、超高級車から売れ始めるのが普通。中国もこれまではそうした状況にあり、ロールスロイスやベントレーなどが良く売れる市場とされていた。
今回のショーでも出品されたヴェイロンがわずか数十分で売約済みとなるなど、展示された高級車が次々に売約済みになっていったという。
最近の中国市場は、ミドルセダンの販売台数が増えることで市場全体が大きく盛り上がってきたが、自動車メーカー各社はさらにその次の状況を読み、普通のユーザーが普通にクルマを持つ時代がくることを想定したクルマ作りを進めている。
幅広いユーザー層を対象とするには、低価格のクルマであることが必要で、手頃なサイズで手頃な価格のコンパクトなクルマが求められる時代が到来しつつある。中国メーカー各社が揃ってコンパクトカーを市場出品していたのは、それに対応するためだ。
中国メーカーに限らず、トヨタがヴィオス(ベルタ)に続いてヤリス(ヴィッツ)の発売を、またホンダがフィットの発売を表明したことなども、そうした流れの中にあることといえる。
奇端(チェリー)汽車が発表したファイラというコンパクトカーは、一気に7タイプのボディを同時に投入した。2種類の3ドア、5ドア、5ドアのSUV、2ドアクーペ、2ドアオープン、4ドアセダンの4種類で、イタリア人デザイナーを起用したスタイルはなかなかカッコ良い。
モータリゼーションの夜明け
また、ユーザー層が大きく広がることで、クルマに対するニーズも多様化することが予想される。コンパクトカーといっても単なるハッチバックタイプの実用車だけでなく、さまざまなタイプのクルマが求められるようになる。
そうしたニーズに最も端的に対応したのが奇端汽車で、同じプラットホームをベースにイタリア人デザイナーを手を借りて一気に7タイプものクルマを同時に投入してきた。凄まじいばかりの勢いである。
日本でもかつて、トヨタが初代ヴィッツをベースに、プラッツやbB、ファンカーゴ、イストなど多数のモデルを次々に投入した例があるが、これらは順次投入されていったもの。同時に7タイプものボディを投入するのは、中国メーカーの勢いを示すもの以外の何物でもない。
ほかにも天津一汽がTFCシリーズの4タイプを同時に投入するなど、コンパクトカーに対する力の入れ方は相当なものがある。
日本で1960年代にサニーやカローラが発売され、あるいは韓国で1970年代から1980年代にかけてポニーやフェスティバが発売され、モータリゼーションが急速に進展した時期があった。現在の中国は、そうしたモータリゼーションの夜明けを迎えようとしている時期のように思えた。
中国の三大自動車メーカーのひとつ第一汽車グループの天津一汽も4タイプのボディを持つTFCと呼ぶコンパクトカーのシリーズを同時に発表した。奇端汽車には及ばないが、これも中国メーカーの勢いを示す例だ。