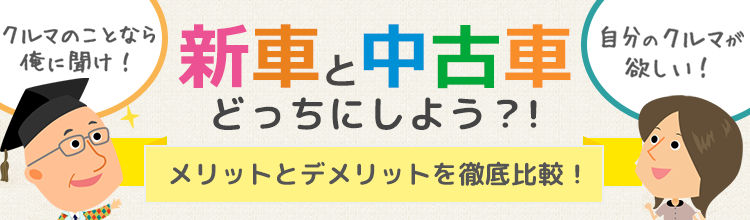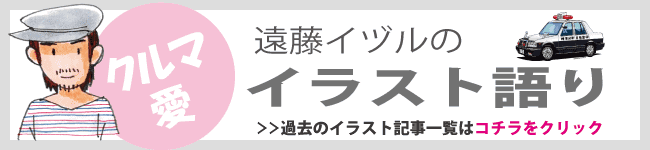
「みんなの街のはたらくくるま」第10回 いすゞ エルフ 吸上車(バキュームカー)
わたしたちの生活を支えている「はたらくくるま」にスポットを当ててイラストとともにご紹介するこのコーナー。第10回は、吸上車(きゅうじょうしゃ=バキュームカー)をお送りいたします。
お食事中にご覧の方はごめんなさい。でも、このクルマなくして、日本の近代化は無かったとも言われる、重要な「はたらくくるま」です。タンク内を真空ポンプで空気を薄くして汲み上げるバキュームカー(吸上車)は、トラックの背中に楕円形のタンクを背負い、パイプがそれを取り巻いているのが特徴です。

都市部に限らず日本各地ではトイレの水洗化が進み、バキュームカーを以前ほど見かけなくなりました。もちろんまだまだ必要なエリアも多いですし、家庭向けの用途だけでなく仮設トイレでの作業や、各種下水処理関連施設の定期メンテナンスなどに使用されるため、これから先も完全になくなることはありません。
保有するか業者に委託するなどの違いはありますが、各自治体における重要な清掃事業のひとつとなっています。そう、バキュームカーは、今なおわたしたちの生活に必須の「はたらくくるま」でい続けているのです。
◆懐かしきトミカの記憶
ところで、1970年代生まれの世代が子供の頃は、都市部でもバキュームカーをよく見かけ、男の子にも案外人気のあるクルマだったと思います。実際にトミカのミニカーでは、バキュームカーは長年にわたって常に製品ラインナップが行われたロングセラーで、安定した人気のある商品でもありました。
 そのトミカのバキュームカーで印象深いのはいすゞ エルフと、トヨタ ダイナなのですが、トミカのイメージとしてぼくが持っていたのは、今回絵にした3代目エルフ+タンクの上にホースリールを備えたモデルだったのです。
そのトミカのバキュームカーで印象深いのはいすゞ エルフと、トヨタ ダイナなのですが、トミカのイメージとしてぼくが持っていたのは、今回絵にした3代目エルフ+タンクの上にホースリールを備えたモデルだったのです。
でも、1972年に発売されていた2代目エルフのバキュームカーはホースリールを持たないタイプで、1980年から2001年まで【不動の製品番号18番】として知られた3代目ダイナが、ホースリールがあるタイプでした。記憶というのはごっちゃになっているものですね。
ということで、描いたのは3代目エルフとホースリール付きタンクを持つ姿(TLD23ZEB)をチョイスしました。色はやはりミニカーでもおなじみ、白いキャビンに古い東京都の「いちょうマーク」、そして緑色のタンクですね。
余談ですがバキュームカーという名称は和製英語で、登場当初「真空車」と呼ばれていたのがそのまま英語に置き換えられた、とされています。真空車というのはバキュームカーの構造を言い得て妙で、感心してしまいました。なお、各自治体では「吸上車(きゅうじょう)車」が正式名称です。
【イラスト/文 遠藤イヅル】
フリーのカーイラストレーター/ライター。東京都出身。自動車雑誌、WEBサイトにクルマをテーマにしたイラストや記事を多数提供。世界各国の生活感があるクルマを好み、20年間で18台のクルマを乗り継ぐ。クレイジーなほど深くて混沌としたクルマ知識を持つ元自動車系デザイナー。自身のクルマ体験をもと、独創的な視点で切り込むイラストやインプレッション記事は、他にないユニークなテイストとして定評がある。2015年7月現在の愛車はプジョー309SI。最新の掲載誌は遠藤イヅルのfacebookで確認!