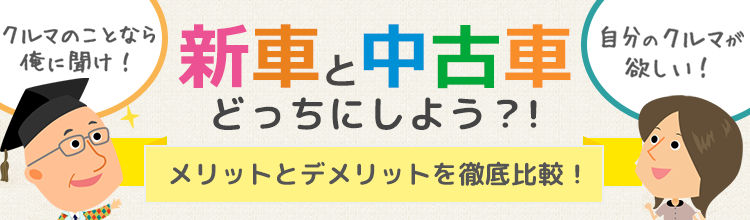トヨタが社会貢献活動の一環として行なっている子供向けの科学工作教室「科学のびっくり箱! なぜなにレクチャー」が開催された。このイベントはトヨタ技術会の有志が講師を務め、子供たちに楽しみながらもの作りの大切さや科学の楽しさを伝えていくというものだ。
1996年にトヨタ創立60周年を記念した社会貢献活動として始まり、今年で11年目を迎えるイベントで、2005年度までに全国各地で198回も開催されているという。プログラムの内容は会場によって異なるが、空力ボディやからくり自動車など、クルマ関連のものはもちろん、ホバークラフトや手作り飛行船など全9種類の教室が用意されている。
わかりやすく興味を持てる工夫が満載されている
9月3日の東京・国立科学博物館の回では、二足歩行ロボット/空力ボディ/ホバークラフト/衝突安全ボディの4つのプログラムが行なわれた。そのなかでも空力ボディと衝突安全ボディの2つのプログラムに注目したい。
衝突安全ボディでは、ビデオで衝撃吸収ボディGOAの構造を学んだ後、簡単な実験装置で衝撃力の変化を実際に観察する。その後、硬さの異なる数種類の紙で作ったいろいろな衝撃緩衝材を模型自動車に取り付け、衝撃力の少なさを比較していくコンテスト形式で進められていく。
また空力ボディでもミニ風洞実験装置を使った本格的な実験を行ない、クルマのカタチが空気の流れに及ぼす影響を観察。そして空気の流れを考えながらボディ模型を制作し、空気抵抗の少なさを競う形式で、子供たちにとってもわかりやすく興味をもてる内容で構成されている。
この「科学のびっくり箱! なぜなにレクチャー」は、今後も全国各地で開催される予定だ。対象は主に小学校高学年(4〜6年生)で参加費は、なんと無料だというから驚きだ。所要時間も2時間程度なので、是非参加してみるといいだろう。