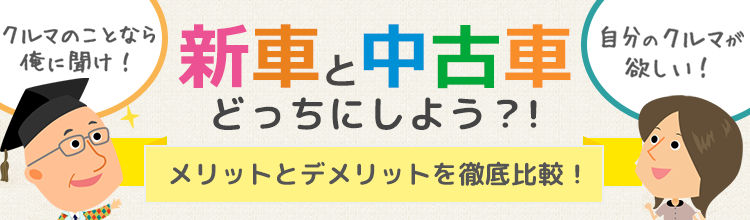急拡大を続ける中国の自動車市場
中国の自動車市場は急速に拡大している。年間の新車販売台数に関する正確な統計はないとも言われているが、メーカーの出荷台数がほぼ販売台数に相当するので中国汽車工業会がまとめたその台数を見ると、2005年の段階で592万台とすでに日本を上回ってアメリカに次ぐ世界第二の自動車市場に成長しており、2007年には前年比で21.8%も台数を伸ばして888万台に達している。
さすがに今年は伸び悩むのではないかとの見方もあったが、第一四半期の台数は30%もの増加を続けているとのこと。オリンピックの開催を控えて中国の自動車市場はまだまだ拡大している状態にある。
最近では、経済的に豊かな沿岸部だけでなく内陸部でも自動車需要が盛り上がっていて、伸び率ではこれまでの販売実績が低かった内陸部のほうが高いという。13億人もの人口を抱える大市場だけに、伸びる余地はまだまだ大きいといえる。
中国の自動車メーカーは、第一汽車、上海汽車、東風汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、駿威汽車、長城汽車などが大どころで、これらのメーカーはほとんどが欧米や日本の自動車メーカーとの技術協力の元にクルマ作りをしているが、このほかにも中小の自動車メーカーが多数存在しており、北京モーターショーにもいろいろなメーカーが出展していた。
自動車メーカーは徐々に整理統合が進んでいくと見られるが、提携する海外メーカーもいずれは世界最大の自動車市場になるはずの中国から簡単に手を引くことは考えられず、外国の自動車メーカーも含めて競争が進んでいくことになる。
そんな中で相当に厳しい販売合戦が繰り広げられているとのことで、発売当初に大人気を集めて何カ月もの納車待ちが発生した車種も、モデルが古くなって競合車に対して魅力薄になると、たちまちのうちに大幅な値引きを迫られることになるという。
整備されて走りやすい北京市内
今回の取材では北京を見てきただけだったが、北京市内は4車線程度の幅の広い道路が良く整備されていて、全体に走りやすい印象だった。放射状に伸びる高速道路や環状道路の整備も進んでいて、道路網の充実度は東京とは比較にならないくらいに進んでいた。社会主義国家なので、道路建設などは方針が決まればある程度強制的に進められるといったことも理由だろう。
ただ、交通集中による渋滞はけっこう多いようで、道路の整備がクルマの増加に追いつかないのは世界中で共通の問題である。
北京市内の空気は、特にきれいという印象ではなかったが、20年ほど前のバンコクで浄化されていない排気ガスをまき散らす日本車がいっぱいだったことを思い出すと、排気ガス規制の実施されている今の北京のほうがずっときれいな空気に思えた。
数年前までは自転車があふれていたという北京市内も、今では自転車の台数は少なくなり、完全にクルマ中心の道路交通になっていた。幹線道路は駐車違反の取り締まりが厳しいためか、違法駐車するクルマは全くない状態で、それだけ走りやすい印象だった。
交通マナーは必ずしも良いとはいえない状態。針路変更などはほとんど方向指示器を使わずにやるのが普通で、かなり強引な割り込みも行われていた。また割り込みに対しては相当に頑張って簡単に譲らないクルマも多かった。
ただ、一度割り込まれたなら、その後は追い上げて車間を詰めるようなクルマは見受けられず、後まで根に持たないのはマナーの良さというべきかも知れない。これは私の知る限り、台湾でもタイでもフィリピンでも同じで、割り込まれた後で車間を詰めるのは日本だけの特殊な対応のようだ。日本人もアジアのマナーを見習うべきである。